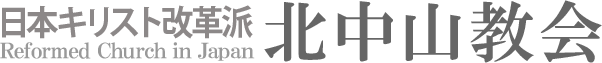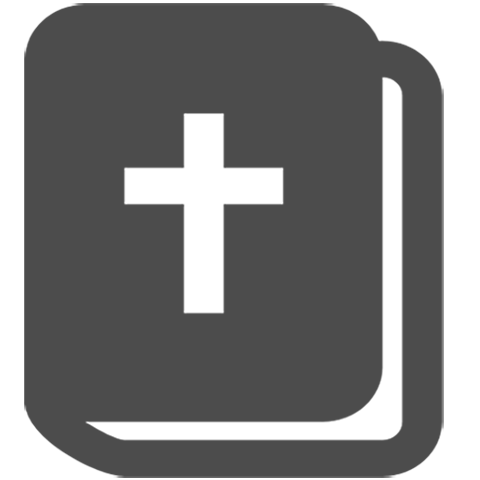時が来ました
- 日付
- 説教
- 尾崎純 牧師
- 聖書 ヨハネによる福音書 17章1節~5節
1イエスはこれらのことを話してから、天を仰いで言われた。「父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を現すようになるために、子に栄光を与えてください。2あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために、子はあなたからゆだねられた人すべてに、永遠の命を与えることができるのです。3永遠の命とは、唯一のまことの神であられるあなたと、あなたのお遣わしになったイエス・キリストを知ることです。4わたしは、行うようにとあなたが与えてくださった業を成し遂げて、地上であなたの栄光を現しました。5父よ、今、御前でわたしに栄光を与えてください。世界が造られる前に、わたしがみもとで持っていたあの栄光を。日本聖書協会『聖書 新共同訳』
ヨハネによる福音書 17章1節~5節
イエスが話を終えて、最後の祈りに入りました。
この17章は全部祈りになります。
そして、この祈りは三通りに分けられます。
第一の祈りが今日のところで、ご自分のことを祈っておられます。
第二の祈りは6節から19節までで、弟子たちのための祈りです。
そして、第三の祈りが20節から26節で、これから後の時代の、すべてのクリスチャンのための祈りです。
今日はその最初の、ご自分のための祈りなんですが、「父よ、時が来ました」と祈りはじめます。
この「時」というのは、今までにも何度も出てきましたが、イエスが逮捕され、十字架にかかる時ですね。
そして、それについて、「あなたの子があなたの栄光を現すようになるために、子に栄光を与えてください」と祈っています。
これが注目したいところなんですが、イエスは、十字架で苦しむことになる自分を神が支えてくれることを祈ったのではないんですね。
イエスはご自分が栄光を現すことを求めました。
十字架のどこに栄光があるでしょうか。
イエスはこれから、偽りの裁判を受けさせられて、侮辱され、裸にされて、鞭うたれて、さらし者にされて、死ぬんです。
けれども、それは罪のないイエスが人の罪を引き受けることでした。
ですから、十字架には、罪の赦しがあります。
救いがあります。
十字架には、罪人を救うという、神にしかできない、神の栄光があるんです。
イエスはここで、人の救いを祈っておられるんです。
今日、この部分の祈りはご自分のための祈りであると申し上げましたが、正しくは、人の救いのための祈りです。
人の救いをご自分が成し遂げることができるようにと祈っておられるんです。
続けてイエスは、「あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました」と言っています。
栄光を与えられると言っても、それは単なる名誉ではないんですね。
権能なんです。
どのような権能なのかと言うと、人を罪と滅びから救い出して、永遠の命を与える権能であるということが続けて言われています。
このところの御言葉はマタイによる福音書でのイエスの最後の言葉を思い出させます。
「わたしは天と地の一切の権能を授かっている。だから、あなたがたは行って、すべての民を私の弟子にしなさい」という言葉ですね。
しかし、マタイによる福音書のこの個所でイエスがこう言ったのは、十字架にかけられて復活した後です。
復活した後で、これくらいの大きなことを言うのなら分かります。
何しろ復活したんですから、もうそれだけで、「天と地の一切の権能を授かっている」というくらいのことだと言えるかもしれません。
けれども、今日の個所では、まだ十字架に付けられてもいないイエスが、「あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました」と、過去形で言っているんですね。
それは未来のことのはずです。
ですが、未来のことであったとしても、確実にそうなると信じている時には、それを過去形で表現することがあるんですね。
旧約聖書の詩編などにも、そのような表現が時折見られます。
そもそも、ヘブライ語には、時間を現す表現が完了形と未完了形しかありません。
神の言葉が、もう既に完了したか、まだ完了していない、これから完了するか、そのどちらかしかないんですね。
イエスは、このことは必ず実現するということで、ここでこのような表現を使っているんですね。
そして、後になって、実際にそうなっていったということなんですね。
イエスの、人を救う権能は、イエスが神から「ゆだねられた人」に現れます。
それは私たちの主観では、私たちがイエスを信じるかどうかの問題ですが、神の側では、神がイエスに委ねた人に信仰が芽生えてくるんですね。
この礼拝に出席しているというのも、同じようなことですね。
私たちの主観では、私たちが礼拝に行こうと思ってここに来たわけですが、神の側からすると、神が招いてくださったから、私たちがここに来ることができたわけです。
ですから、今はまだ信仰をもっていない方々も、神がイエスに委ねようとして礼拝に招いてくださっていると言えます。
実際に、神がその人をイエスに委ねるのがいつの時になるのかは分かりません。
ただ、神の御心は、もうそれが実現したか、これから実現するか、どちらかしかないわけです。
その次のところでは、永遠の命について語られます。
「永遠の命とは、唯一のまことの神であられるあなたと、あなたのお遣わしになったイエス・キリストを知ることです」。
永遠の命と聞きますと、死んで全てが終わりになるのではなくて、肉体が死んだ後も、何らかの形でこの私という存在が続いていく、というようなイメージを持ちますが、そうではないんですね。
永遠の命とは、神とイエスを知ることです。
ということは、永遠の命とは、死んだ後のことではなく、今からでも生き始めることができるものなんですね。
しかし、どうして、「神を知る」ということが「永遠の命」になるのでしょうか。
「神を知る」ということと「永遠の命」というものは全く別次元のものであるように思われます。
そこで一つ言えることは、ヘブライ語の「知る」という言葉は、単に知識として知るということに留まらない言葉だということです。
この言葉は、例えば、男女の性交渉を指して使われることもあるような言葉です。
創世記4章に、「アダムは妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み」ということが書かれている通りです。
知ると言っても、頭の中での単なる知識ではないんですね。
ですから、旧約聖書以来、神を知ることは、それ自体に人を救う力があることが言われてきました。
神を知ることはこの世のことを知ることとは違うんですね。
単なるデータの一つではないんです。
データではなくプログラムだと言ったらいいでしょうか、頭の中に留まっているだけではなくて、私たちの内で力を持って働くんですね。
もちろん、聖書に書かれている神についての知識を、単なる情報として扱うこともできます。
ただ、そうではなく、その知識を自分のこととして、自分の内に受け入れる時、神とイエスが私たちに与えようとしておられるところの永遠の命というものが実際に立ち上がるという仕組みになっているということですね。
神を知ることは知識と言えばそうなんですが、大事なのは、自分の内に受け入れることです。
これについて、こういう話があります。
シカゴ大学の神学部では、毎年、偉大な神学者を招いて、講義をすることになっていたそうです。
ある年、パウル・ティリッヒ博士が招かれました。
このティリッヒという人は、今でもしっかりと名前が残っている、非常に有名な神学者ですが、本人は信仰があるつもりの人なんですけれども、神学で人間の意識を整えようという、結局のところ、何が人間にとってプラスになるのかを第一に考える人で、神学者というより哲学者と言った方が近いような人でした。
ティリッヒ博士は、2時間半にわたって、イエスの復活が偽りであることを証明しようと講演しました。
彼は様々な学説を次々と引用しながら、復活というものは存在せず、教会の伝統に過ぎないと言いました。
そして最後に、質問を受け付けたんですね。
静かなホールの中で年老いた牧師が立ち上がりました。
「ティリッヒ博士、一つ質問があるんですが」。
そう言いながら年老いた牧師は紙袋の中からリンゴを取り出し、食べ始めました。
食べながら、質問するんですね。
「ティリッヒ博士、私の質問は簡単な質問です。
私はあなたの本を読んだことがありません。
私は聖書をギリシャ語で読むことができません。
ニーバーやハイデガーについて何も知らないんです」。
年老いた牧師はリンゴを食べ終えました。
そして、言いました。
「私が知りたいのは、今食べたこのリンゴです。
今食べたこのリンゴは、苦かったですか、甘かったですか」。
ティリッヒ博士はしばらく間を置いて、正しい答えを返しました。
「私はその質問に答えることはできない。
あなたのリンゴを味わっていないのだから」。
年老いた牧師はティリッヒ博士を見上げて言いました。
「あなたはイエスを味わったことがありますか」。
1,000人を超える聴衆の拍手と歓声が沸き起こりました。
ティリッヒ博士は足早に講壇を降りました。
大事なのは、味わうことです。
頭の中で知識をいじることに意味はありません。
それは結局、神ではなく自分を主にしてしまうことです。
味わうこと、いただくこと。
考えてみれば、イエスは、ご自分自身を味わわせてくださいましたね。
イエスは最後の晩餐の席で、弟子たちに、自分の肉を食べるように、血を飲むようにと言って、パンとぶどう酒を差し出しました。
パンは、これからあなたがたのために裂かれる私の肉である。
ぶどう酒は、これからあなたがたのために流される、私の血である。
そう言って、パンとぶどう酒を弟子たちに食べさせました。
ご自分自身の肉と血を、ご自分の命を食べさせてくださったんです。
私たちはそれに基づいて、今でも、それぞれの教会で聖餐式を執り行っています。
それはイエスがそうするようにと言われたからそうしているのですが、しかし、それは、そうしなければならないようなことだったのでしょうか。
つまり、パンとぶどう酒を弟子たちに与えるのではなく、単に、私が命を懸けてあなたを救う、それを信じなさいと言っただけでも良かったのではないでしょうか。
それだけでも良かったのかもしれません。
でも、そうはしなかったんです。
イエスは、弟子たちに、ご自分を味わわせたかったんです。
味わってこそ、分かることがあるからです。
最後のところでイエスは、ますますヒートアップしていくような感じですね。
「わたしは、行うようにとあなたが与えてくださった業を成し遂げて、地上であなたの栄光を現しました」。
これは、イエスが今までにしてきた様々な神の働きのことを言っているのではありません。
ここの「業」という言葉は単数形なんです。
ですからこれは、十字架の救いの業のことを言っています。
だからここで、「成し遂げた」という言葉が使われていますね。
それは後になって実際に、イエスが十字架の上で口にした言葉です。
本当は未来のことなんですが、必ずそうなることですので、ここでは過去形です。
イエスはもう今、十字架の救いを成し遂げた気持ちです。
だから続けて5節で、最後の最後、天に昇っていくことを求めるんですね。
「父よ、今、御前でわたしに栄光を与えてください。世界が造られる前に、わたしがみもとで持っていたあの栄光を」。
これは、今、もう、すべて成し遂げて天に昇ろうとしている気持ちでそう言っているんですね。
そして、実際にその通りになります。
その通りになったんです。
その方が、私たちに言っておられます。
私を知りなさい。
私を受け入れ、味わいなさい。
味わわせていただきたいと思います。
そこに救いがあります。