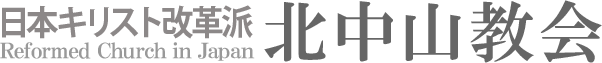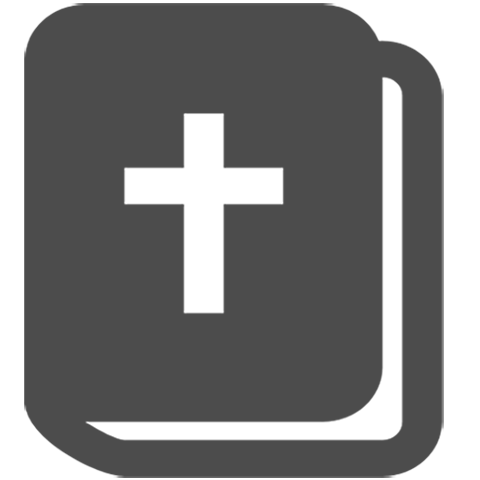わたしは既に世に勝っている
- 日付
- 説教
- 尾崎純 牧師
- 聖書 ヨハネによる福音書 16章25節~33節
25「わたしはこれらのことを、たとえを用いて話してきた。もはやたとえによらず、はっきり父について知らせる時が来る。26その日には、あなたがたはわたしの名によって願うことになる。わたしがあなたがたのために父に願ってあげる、とは言わない。27父御自身が、あなたがたを愛しておられるのである。あなたがたが、わたしを愛し、わたしが神のもとから出て来たことを信じたからである。28わたしは父のもとから出て、世に来たが、今、世を去って、父のもとに行く。」29弟子たちは言った。「今は、はっきりとお話しになり、少しもたとえを用いられません。30あなたが何でもご存じで、だれもお尋ねする必要のないことが、今、分かりました。これによって、あなたが神のもとから来られたと、わたしたちは信じます。」31イエスはお答えになった。「今ようやく、信じるようになったのか。32だが、あなたがたが散らされて自分の家に帰ってしまい、わたしをひとりきりにする時が来る。いや、既に来ている。しかし、わたしはひとりではない。父が、共にいてくださるからだ。33これらのことを話したのは、あなたがたがわたしによって平和を得るためである。あなたがたには世で苦難がある。しかし、勇気を出しなさい。わたしは既に世に勝っている。」日本聖書協会『聖書 新共同訳』
ヨハネによる福音書 16章25節~33節
ここのところがイエスの話の最後です。
次のところからは祈りになりますので、お話はここで最後になります。
今日の最初のところにあるとおり、イエスは以前には、基本的にたとえで話してきたわけです。
けれども、「もはやたとえによらず、はっきり父について知らせる時が来る」と言っています。
普通に考えると、はっきり知らせたからと言って、相手が理解してくれるのかどうかは分からないわけですが、この場合、分かるようになるということですね。
はっきり知らせると、弟子たちは変わるんですね。
26節に、「その日には、あなたがたはわたしの名によって願うことになる」とあります。
「その日」というのは今までの話からすると聖霊が弟子たちに送られる日ですね。
その聖霊の働きに、人に神のことを理解させる働きがありましたので、弟子たちは神のことをはっきり理解するようになるわけです。
そして、父について知らせてくれるのは聖霊なんですが、父なる神と神の子イエスと聖霊は一つだという話がすでにありましたので、わたしがあなたがたに知らせる、と言っても良いわけです。
ただここで、神のことを理解した弟子たちが何をするのかというと、イエスの名によって願うことになると言われています。
神に祈るに当たって、イエスの名によって祈る、イエスの名義で祈ることになる。
この話は、このすぐ前のところにも出ていました。
このすぐ前のところで、イエスはご自身のお名前を使っていいということを言っていました。
イエスが名義を貸してくれたわけです。
ただ、その名義を実際に使うようになるのは、聖霊が送られてからなんですね。
聖霊が父についてはっきり知らせてくれてからです。
父というのは神のことですね。
ということは、神のことを父と呼んでいるイエスは神の子だということになります。
イエスはそれらを、今まではたとえで話してきました。
だとすると弟子たちは、神が父だというのもたとえだと思っていたかもしれません。
しかし、聖霊が、それはたとえではなかった、本当のことだと知らせます。
そうすると、弟子たちは、イエスの名によって祈ることが許されているわけですから、それは当然、イエスの名によって祈ることになるでしょう。
何もなしに祈るより、神の子の名義で祈った方がいいに決まっています。
これが、イエスの父のことをはっきり知ったことによる変化です。
これがもし、神が父だというのがたとえだと思っていたとしたら、イエスの名によって祈るということはしないわけです。
イエスの父が神だというのは、聖霊によって知らされるからこそ、分かることで、普通に考えてそんなことは分かるはずがありません。
けれども、聖霊は、人間には分からないはずの神の次元のことを理解させてくださるんですね。
そして、神の子の名義で私たちが祈ることができるようにしてくださるのです。
そして、神の子の名義で祈る効果は絶大なんですね。
イエスは、「わたしがあなたがたのために父に願ってあげる、とは言わない」と言っています。
自分に代わってイエスに祈っていただく必要は無くなるわけです。
つまり、イエスの名による祈りは、祈りとして完全なんですね。
宗教改革者のジャン・カルヴァンは、私たちがキリストの名によって祈ることについて、「われわれはあたかもイエスの口によって祈るようなものである」と言っています。
完全なんです。
だから、イエスに祈っていただく必要はないんです。
ここでイエスは、また違ったことを言います。
それが27節ですね。
「父御自身が、あなたがたを愛しておられるのである」。
祈りが聞かれると言っても、それは私がイエスの名によって祈ったからで、神にとって私自身はどうでもいいというのなら悲しいですが、そうではないんですね。
神は私たちを愛してくださいます。
それは、「あなたがたが、わたしを愛し、わたしが神のもとから出て来たことを信じたからである」ということですね。
これは簡単な話です。
神はイエスの父です。
親にとって、自分の子どもを理解して、自分の子どもを愛してくれる人ほどありがたい人はいません。
まして、神にとって、イエスをこの世に送るというのは、自分の息子が理解してもらえるはずのないところに、世の罪、人の罪の真っただ中に愛する息子を送ることです。
神にとって、イエスを愛してくれる人がいることが、どれだけありがたかったでしょうか。
私の高校時代の担任の先生に、息子さんが重いダウン症の方がおられましたけれども、お子さんが小学校低学年時代、学校で、トイレに行きたくなったんだけれども、一人で用を足せない。
その時、同じ学年の子が手伝ってくれて、お尻まで拭いてくれて、助けてくれたんだそうです。
その先生は、その時のことを、「今まで生きてきて、これほどうれしいことはなかった。自分の子は誰にも受け入れられないだろうと思っていた。自分が結婚した時よりも嬉しかった」と言っていました。
それは嬉しかっただろうなと思いますね。
神が私たちを愛してくださるのも同じことです。
理解されるはずのない我が子を理解し、愛してくれる人がいる。
それは神にとっても大いなる喜びなんですね。
だから、神は抑えきれないくらいの愛で、私たちを愛しておられます。
最後にイエスは、ご自分のことを言います。
「わたしは父のもとから出て、世に来たが、今、世を去って、父のもとに行く」。
これは、今までは弟子たちに理解されなかった言葉でした。
けれども、ここで弟子たちは言います。
「今は、はっきりとお話しになり、少しもたとえを用いられません。あなたが何でもご存じで、だれもお尋ねする必要のないことが、今、分かりました。これによって、あなたが神のもとから来られたと、わたしたちは信じます」。
弟子たちはイエスの言葉がたとえではないと受け止めました。
そのままの意味で受け取りました。
続けて、「あなたが何でもご存じで、だれもお尋ねする必要のないことが、今、分かりました」と言っていますが、これは、イエスが、「だれにも尋ねられる必要のないことが、今、分かりました」という言葉です。
「だれにも尋ねられる必要のない」というのはつまり、そんなこと聞かなくても、イエスは明らかに神の子だ、ということです。
弟子たちはもう、はっきりと知ったつもりになっています。
そこで、イエスは言います。
「今ようやく、信じるようになったのか」とありますが、原文には「ようやく」という言葉はありません。
ここは、「今、信じると言うのか」という言葉です。
まだ、聖霊は送られていません。
ですから、弟子たちが言ったことはフライングです。
それをたしなめているのが、「今、信じると言うのか」という言葉です。
まだだよ、ということです。
続けてイエスは言います。
「だが、あなたがたが散らされて自分の家に帰ってしまい、わたしをひとりきりにする時が来る。いや、既に来ている」。
「自分の家に帰ってしまう」とありますが、「家」という言葉も原文にはありません。
直訳すると、「自分自身のところへと散らされる」となります。
これからイエスが逮捕されると弟子たちは皆、逃げ出してしまいます。
そのことを、「自分自身のところへと散らされる」と言っています。
弟子たちは今までイエスに従ってきましたが、イエスを見捨てて、皆それぞれ、元の通り、自分の思いに従って生きるようになり、バラバラになってしまうということです。
そのような形で、イエスはひとりきりになる。
けれども、イエスには神がいつも共にいてくださっているとイエスは言います。
これは、一人になっても神がおられるから寂しくないということではないでしょう。
神がイエスと共にいる。
安心してそのイエスのもとに戻ってくるように、弟子たちを諭しているんだと思います。
33節はお話の最後のしめくくりです。
「これらのことを話したのは、あなたがたがわたしによって平和を得るためである。あなたがたには世で苦難がある。しかし、勇気を出しなさい。わたしは既に世に勝っている」。
イエスは弟子たちに平和を与えようとしておられます。
弟子たちには世で苦難があるからです。
苦難を取りのけてくださるのではありません。
苦難の中でも平和でいられるようにしてくださるのです。
そもそも、この世では、私たちも含めて皆、自分の思いに従って生きていますから、苦難というのは避けられません。
そして、苦難が大きければ大きいほど、私たちは自分自身のところに散らされます。
自分中心になります。
自分が第一になります。
聖書が罪だと言うのはそのことですが、私たち自身、そのような罪の中を生きるしかない者です。
これは、私たちに解決できることではありません。
しかし、その私たちに、「勇気を出しなさい」と言われています。
この言葉は、他のところでは「安心しなさい」と訳されている言葉なのですが、イエスは、何の根拠もなくただ私たちに頑張れを言っておられるのではありません。
「わたしは既に世に勝っている」とイエスは言います。
イエスはこれから十字架に付けられます。
世の人々はイエスを受け入れませんでした。
人々の中には、イエスに期待する人もいました。
自分たちの国を支配している外国勢力を、イエスが追い出してくれるかもしれない。
国自体が外国に支配されるという苦難の中にあった時代です。
苦難に遭うと、自分中心になります。
イエスが逮捕されると、そんな力の無い人間に何もできるはずはないということで、人々は手のひらを返します。
イエスはまさに、世の罪に負けたように見えます。
しかし、イエスは、十字架の後、ご自分が復活することを知っておられました。
それが、「わたしは既に世に勝っている」ということです。
世がどれだけ横暴になり、自分中心になっても、イエスを思い通りにすることはできませんでした。
そして、このことは、イエスが、ご自分の力を自慢するためにした話ではありません。
弟子たちを安心させるためです。
弟子たちにも苦難があります。
そして、結局のところ、最終的には、この何年後か何十年後かに、弟子たちのほとんどは、殉教の死を遂げます。
弟子たちの生涯は、イエスの弟子であるがために、苦難続きであったと言えます。
しかし、弟子たちは誰も、苦難に負けることはなかった。
世の罪に打ち勝った方の弟子であり通したからです。
だから、苦難に負けることがなかった。
弟子たちの心には、いつも平和があった。
弟子たちは誰も、弟子であることをやめませんでした。
弟子をやめれば、イエスの弟子であることで苦難に遭うことはなります。
しかし、私たちが生きることというのは、そもそも、苦難の中を生きることです。
何らかの形で、苦難というのは必ずやってきます。
そして、苦難の原因である罪を、私たちはどうにもできません。
その中を、それでも平和に生きることができるとするなら、世の罪に打ち勝った方の弟子であること以上のことはありません。
苦難にあっても、弟子たちは平和を得ていたんです。
だから、弟子であり続けた。
殉教はしましたが、それは、逃げなかったということです。
殉教するに当たっても平和は失われなかったという証しです。
私たちは、生きる上での苦難というものを当たり前のものだと見なしがちです。
たしかに、それはそうです。
しかし、苦難の中でも、ゆるがされない平和を生きる道があります。
それは、ゆるがされない方と共に生きることです。
14世紀、カトリックのドミニコ会の修道士にタウラーという人がいました。
タウラーがある日、ホームレスに会って言いました。
「友よ、神様がよい日を与えられるように」。
ホームレスが答えました。
「神様のお陰で、今日までに悪い日は一日もありません」。
そこでタウラーは言った。
「友よ、神様があなたを幸福にされますように」。
「神様のお陰で、私は不幸になったことがありません」。
そこでタウラーは驚いて、「それはどういう意味ですか」とたずねました。
ホームレスは言いました。
「天気のよい日は神様に感謝し、雨が降れば神様に感謝し、ものが豊かにあれば神様に感謝し、お腹がすけば神様に感謝するからです。神のみこころこそ、私が行いたいことであり、神を喜ばせることが私の喜びなのです。私が不幸でもないのにどうして不幸だと言えましょうか」。
タウラーは驚いてこの男を見て、「あなたは誰ですか」と聞きました。
「私は王様です」と答えたので、「あなたの王国はどこですか」と聞きかえしました。「私の心の中です」。
そう、私たちにとって、結局、私たちの心がすべてです。
その私たちに、安心して、平和を選び取りなさいとイエスは言っておられます。
今日の御言葉を心に留めましょう。
安心して、世に出て行きましょう。
わたしたちは既に、キリストにあって、世に勝っているのです。