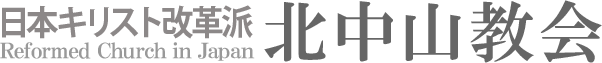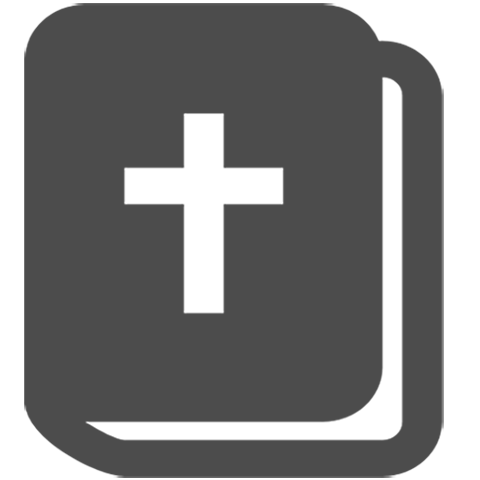墓から走り、墓に走る
- 日付
- 説教
- 尾崎純 牧師
- 聖書 ヨハネによる福音書 20章1節~10節
1週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして、墓から石が取りのけてあるのを見た。2そこで、シモン・ペトロのところへ、また、イエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。「主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか、わたしたちには分かりません。」3そこで、ペトロとそのもう一人の弟子は、外に出て墓へ行った。4二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方が、ペトロより速く走って、先に墓に着いた。5身をかがめて中をのぞくと、亜麻布が置いてあった。しかし、彼は中には入らなかった。6続いて、シモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、亜麻布が置いてあるのを見た。7イエスの頭を包んでいた覆いは、亜麻布と同じ所には置いてなく、離れた所に丸めてあった。8それから、先に墓に着いたもう一人の弟子も入って来て、見て、信じた。9イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を、二人はまだ理解していなかったのである。10それから、この弟子たちは家に帰って行った。日本聖書協会『聖書 新共同訳』
ヨハネによる福音書 20章1節~10節
イエスが復活したのはここにある通り、「週の初めの日」です。
ただ、復活と言いますと、私たちは、使徒信条で覚えている表現がありますね。
「三日目に死人の内よりよみがえり」ということですね。
聖書の中にもよく出てくる表現です。
ただ、「三日目」とは書かずに、「週の初めの日」と書いた。
このように書かれますと、いろいろと考えることがあります。
今日も、「週の初めの日」です。
日曜日です。
日曜日には教会で礼拝を行うわけですが、それは当たり前のことではないんですね。
もともとは、礼拝をするのは土曜日でした。
神様が六日間かけてすべてのものをお造りになられて、七日目に休まれた。
そのことになぞらえて、一週間は七日間で、七日目の土曜日に仕事を休んで、礼拝する。
ということは、日曜日は平日なんです。
仕事の日なんです。
でも、キリスト教会では、日曜に礼拝します。
それは、復活したイエスが弟子たちに会いに来てくださったのが日曜だからです。
私たちの礼拝は、イエスに会うことなんです。
ただ、日曜に礼拝するというのはどれくらい大変なことだったかと思うんですね。
今では、世界中どこでも、一週間は七日間で、日曜は休みですが、それは聖書に基づくことです。
日本だと、休みというのはもともとは、お正月休みと盆休みだけでした。
一週間が七日間というのも、週に一日休むというのも、もともとは、聖書を読んでいたユダヤ人だけがやっていたことです。
そして、もともとは、仕事を休んで礼拝をする日というのは、土曜日でした。
とこどが、イエスの弟子たちは、日曜日に礼拝するということを始めたんです。
世の中では、日曜というのは仕事の日です。
平日なんです。
それでも礼拝をするとなると、どうすればいいのか。
今日の場面のように、仕事が始まる前に、朝早く、まだ暗いうちに礼拝するしかありません。
「週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った」と書かれていますけれども、これはキリスト教会の最初の礼拝であると言えるかもしれません。
私たちはというと、この通り、日曜という休みの日に10時30分から礼拝をしています。
それは、世界中どこでも同じようにしていると思います。
しかし、一週間が七日であり、七日の内、週の初めの日は仕事を休んで礼拝する、それを世界中に広めるために、どれほどの年月をかけた、どれほどの苦労があったのかを思います。
感謝して礼拝をささげたいと思います。
さてこの朝、マグダラのマリアと他の女性たちは、イエスの墓に行きました。
マグダラのマリア一人で行ったのではないことは、2節の言葉で、自分のことを「わたしたち」と言っていることから分かります。
しかし、どうして女性たちは墓に行ったのでしょうか。
他の福音書では、イエスの遺体に本来塗るべき没薬が塗られていなかったから、それを塗るためにお墓に行ったんだということが言われますが、この福音書では、そのような話は出てきません。
そして、いずれにせよ、墓には石で蓋がしてあるのです。
また、いずれにせよ、朝、暗い内に行かなければならないことはないでしょう。
日曜は仕事の日ですが、イエスに従っていた婦人たちは、ガリラヤ地方に始まって、イエスと一緒に旅をしてきた人たちです。
ガリラヤの地元では仕事があったかもしれませんが、遠く離れたエルサレムの町で仕事をしていたということもないでしょう。
ではどうして、朝早く、墓に来たのか。
とにかくイエスと共に居たいという思いがそうさせたのでしょう。
ところが、墓から石が取りのけられていました。
墓の中も見たのでしょう。
イエスの遺体がない。
そこでまず、女性たちはシモン・ペトロのところへ走っていきました。
次に、イエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走っていきました。
これを見ると、ペトロともう一人の弟子は、別々のところにいたようですね。
だとしたら、とりあえずペトロだけでもいいのではと思いますが、女性たちは、自分たちが見たことは間違いない、確かに、イエスの遺体がなくなっているということを、男性二人に確認してもらいたかったんだと思います。
証言というのは、二人以上の男性でなければならなかったんですね。
ただ、女性たちにしても、イエスが復活したと考えたわけではありません。
女性たちは言いました。
「主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか、わたしたちには分かりません。」
それを聞いて、ペトロとヨハネは走り出しました。
今日の場面では、走るということがよく言われますね。
女性たちも走ったし、男性たちも走りました。
何か希望があるわけではありません。
むしろ、その逆ですね。
イエスの遺体がないんです。
そのことに、心を乱されて、走り出した。
それまでは、女性たちも、男性たちも、座り込んでいたと言えます。
女性たちは、悲しみの中に座り込んでいた。
せめてもの慰めにと、イエスの墓に向かった。
墓で何をするんでしょうか。
座り込んでいるしかないでしょう。
男性たちはそれもせずに、家から出ることもなかった。
イエスの弟子であるということで逮捕される可能性がありますから、外に出られないのは仕方がないかもしれません。
ただ、それ以前に、弟子たちは、弟子であるのに逃げ出してしまったということがあります。
弟子たちは、墓に行く資格はないんです。
弟子たちにとって、家の中での時間は、どれくらい長い時間だったでしょうか。
前日は土曜日で礼拝の日だったわけですが、弟子たちが礼拝するために会堂に行ったとは思えません。
弟子たちも女性たちも、ずっと家の中にいたんでしょう。
それはどんな時間だったでしょうか。
他の福音書には、まさにこの日曜日にエルサレムを出て自分の町に帰ろうとしていた弟子たちの話が出てきます。
前日は礼拝するための日ですから、長い距離を移動することはできないんですが、この日曜からは平日です。
いずれにしても、ずっとこの町にいられるわけではありませんし、いても仕方ありません。
女性たちにしても、いつまでもイエスの墓の前で座り込んでいるわけにはいかないでしょう。
弟子たちが帰ると言い出せば、ついて行くしかありません。
ガリラヤに帰って、いつかは、イエスのことも遠い昔の思い出になっていくんでしょう。
そのようになっていくことが、だんだん見え始めていた頃かもしれません。
そこに、墓に遺体がないという知らせが届きました。
弟子たちは走り出します。
イエスについての知らせに、飛び起きて走り出した。
弟子たちはまだ、弟子だったと言えるかもしれません。
いや、弟子であることをやめるつもりだったけれども、弟子として復活したということでしょうか。
もう一人の弟子の方がペトロよりも速かったということですが、もう一人の弟子は十字架の時に十字架のそばにいたので、墓の場所を知っていた、ペトロは逃げて隠れていたので、墓の場所を知らなかったということかもしれません。
もう一人の弟子は、墓の中をのぞいて、イエスの遺体がないことを確認しました。
後から着いたペトロは、墓の中にまで入って、亜麻布と頭を包んでいた覆いが残されているのを確認しました。
亜麻布が置かれている、と繰り返されていますが、ここで描かれているのは、イエスのお体だけが消えてしまって、イエスの体に巻かれていた亜麻布がそのまま平らになって置かれているような様子です。
頭を包んでいた覆いというのは、死んだ人の口が開かないように口を閉じておくためのものです。
これは「丸めてあった」と訳されていますが、これも、巻かれたままになっていたということです。
やっぱり、イエスの体だけが煙のように消えてしまって、体に巻かれていたものがそのままになっているという表現なんですね。
亜麻布と頭を包んでいた覆いは離れたところにあったということですが、体を巻いていた亜麻布と、頭を包んでいた覆いが、体と頭の間、首の長さだけ、離れていたということです。
イエスの体だけがなくなっていたんです。
そして、大事なのは、8節で、ペトロの後からもう一人の弟子が墓の中に入ってきたとき、もう一人の弟子は、「見て、信じた」と書かれていることです。
マグダラのマリアも、ペトロも、見たと書かれていますが、信じたとは書かれていません。
もう一人の弟子は、見て、信じたんです。
これは、この福音書の少し先のところになりますが、20章29節に、イエスの言葉がありますね。
「わたしを見たから信じたのか。見ないのに信じる人は、幸いである」。
これは、復活を信じなかった弟子のトマスに対する言葉です。
トマスは、復活したイエスをこの目で見るまで信じないと言っていたんでした。
そのトマスに対して、「見ないのに信じる人は、幸いである」と言われたんですね。
今日の三人は、「見た」と書かれています。
それは、イエスの遺体がないのを確認したということです。
ということは、三人は、復活のイエスを「見なかった」わけです。
それでも、このもう一人の弟子は、見ないで信じた。
イエスの復活を信じた、と言われているんですね。
だから、幸いである、ということなんですね。
そして、この弟子のことが、名前は書かれずに、イエスの愛しておられた弟子だと書かれています。
イエスの愛しておられた弟子というのは、私たちも含めて弟子たちみんなですね。
イエスはどの弟子も愛しておられます。
その意味で、私たちも「イエスの愛しておられた弟子」です。
ヨハネによる福音書は言っているんですね。
この、「イエスの愛しておられた弟子」というのは、ヨハネ自身のことだと考えられていますけれども、自分だけじゃないよ、と。
イエスが愛しておられることが分かれば、あなたも、見ないで信じる幸いな者になれるんだよ、ということなんですね。
マグダラのマリアもペトロも、どうしたらいいのか分からなくなっている状況でも、ヨハネだけはこの時、心の中は、またイエスに会えるかもしれないという希望でいっぱいだったことでしょう。
そのように、どんな状況でも希望を抱くことのできる、幸いな者となることができる。
ただ、どうしてこの時、ヨハネだけは見ないで信じることができたのか。
逆に、マグダラのマリアとペトロは、どうして、信じることができなかったのか。
ペトロもマグダラのマリアも、愛されていたはずです。
ですけれども、ペトロは、イエスの弟子であることを自分から三度も否定してしまったということがありました。
こうなるともう、ペトロは、自分はイエスに愛されているとは、自分からは言えないでしょう。
マグダラのマリアは、イエスを深く愛していました。
だからこそ、朝早くに墓に行ったのでしょう。
ですけれども、それは、すべてが終わったとした上で、それでもなお、イエスのそばにいたいという気持ちだったからです。
自分を愛してくれるイエスは、もういないんです。
イエスに愛されていることを実感できると思って墓に行ったのではありません。
もう全部過去のことですが、愛し愛されていた思い出に浸りたくて、墓に行ったんです。
それに対して、ヨハネは、十字架の下にいたときに、イエスに声をかけられていました。
イエスはご自分の母のマリアを示して、ヨハネに言いました。
「見なさい。あなたの母です」。
マリアが自分の母なら、ヨハネはイエスと兄弟です。
生き別れようと死に別れようと、兄弟が兄弟であることに変わりはありません。
ヨハネだけは、現在進行形で、イエスとの交わりの中にあったんです。
そうすると、何が変わるか。
今日の場面で三人に使われている「見る」という言葉は、それぞれ別の言葉です。
マグダラのマリアが見たという時の「見る」という言葉は、単に目で見ることを意味する言葉です。
ペトロが見たという時の「見る」という言葉は、これも目で見たということなんですが、英語のシアター(映画)という言葉の元になった言葉です。
聞いていた話と同じものを見た、予告編と同じ本編だったということになるでしょうか。
それに対して、ヨハネが見たという時の「見る」という言葉は、深い意味を見出したことを意味する言葉なんです。
そして、この、ヨハネに使われている、「見る」という言葉は、この福音書の最初の方の、1章39節でも使われていました。
イエスの弟子になりたいと思っていた人に、イエスが弟子になることを認めた時の言葉です。
「来なさい。そうすれば分かる」。
この、「分かる」がヨハネの「見る」なんです。
ヨハネだけは本質を見たんです。
だから、分かったんです。
目の前にこういう現実があって、それは、普通に考えればこうだけれども、その奥にある本質はこういうことだ、それが分かった。
目に見える人間の現実の奥に、神の現実がある。
それが見えた。
だから、この状況にも、希望を抱くことができる。
そして、同じことは、私たちにもできる、あなたも目に見える現実の奥に、神の現実を見出すことができる、あなたも愛されているんだから、とヨハネは言っているんです。
ただ、このすぐ後で、不思議なことが言われます。
「イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を、二人はまだ理解していなかったのである」。
すぐ前のところで、「信じた」と言われているのに、ここでは、「理解していなかった」と言われています。
ただここで、何を理解していなかったのかというと、「聖書の言葉」ですね。
それも、「イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉」です。
もう一人の弟子は、イエスの復活は信じました。
けれども、そのもう一人の弟子も、イエスの復活と聖書の言葉を結び付けていなかった。
復活したと信じたけれども、その時、「そう言えば聖書にはこのように書かれていたな。なるほど、それは、その聖書の言葉が実現したということか」、そういうふうには考えなかった。
聖書の言葉は、もう一人の弟子の意識にはなかった。
そういうことです。
せっかく復活があったのに、せっかくそれを信じたのに、どうしてこんなことが言われるのかと言いますと、誰かが復活したというのは、それだけでは、他の人にとってはあまり意味がないですね。
その人は復活した、すごいなあ、良かったなあ、それでお終いです。
しかし、聖書には何と書かれてあるか。
救い主は、あなたがたの代わりに罰を受けて死ぬ。
けれども、救い主は死に押しつぶされてしまうことはない。
神は救い主を復活させる。
そして、いつかの日、神はあなたがたをも復活させ、神の元に取り戻す。
イエスの復活は、イエスに力があることを示すためのものではないんですね。
いつか、私たちも復活して、神の元に取り戻される。
その先触れとして、イエスは復活したんです。
もう一人の弟子は、復活を信じました。
でも、その時、聖書に何が書かれてあるのかは頭になかった。
だから、もう一人の弟子は、信じたと言われているけれども、喜んでいる様子はないですね。
自分のことではないからです。
イエスは復活した、だったら、またイエスに会えるかもしれない、そういうワクワクした気持ちはあったんでしょうが、復活したイエスが目の前にいるわけではないから、喜びは表に出さない。
そのまま、家に帰るんです。
もし、信じるだけでなく、理解できていたなら、家には帰りませんね。
出かけていくはずです。
その後になって、弟子たちがやっていったように、復活をのべ伝えていくんです。
そして、弟子たちが今はまだ理解できていないことを、私たちは理解しています。
イエスの復活は私たちのためであるということ。
私たちも、いつの日か、復活して、神の元に取り戻される。
そのことを保障するために、確かなことだとその目に見せるために、イエスは復活して、逃げ出した弟子たちにこれから会いに来てくださるんですね。
私たちは、この目で見たわけではありません。
しかし、ヨハネは言うんですね。
あなたも、見ないで信じることができる。
あなたも、幸いな者となることができる。
イエスに愛されているから。
あなたも目に見える現実の奥に、神の現実を見い出させていただきましょう。
どんな時も、希望にあふれる道が、そこから始まります。