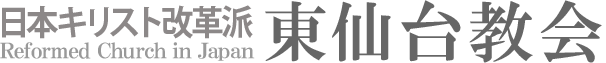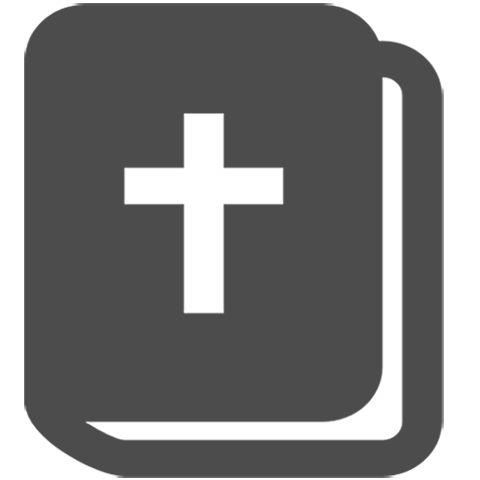その骨は一つも砕かれない
- 日付
- 説教
- 尾崎純 牧師
- 聖書 ヨハネによる福音書 19章31節~37節
31その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは、安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り降ろすように、ピラトに願い出た。32そこで、兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男と、もう一人の男との足を折った。33イエスのところに来てみると、既に死んでおられたので、その足は折らなかった。34しかし、兵士の一人が槍でイエスのわき腹を刺した。すると、すぐ血と水とが流れ出た。35それを目撃した者が証ししており、その証しは真実である。その者は、あなたがたにも信じさせるために、自分が真実を語っていることを知っている。36これらのことが起こったのは、「その骨は一つも砕かれない」という聖書の言葉が実現するためであった。37また、聖書の別の所に、「彼らは、自分たちの突き刺した者を見る」とも書いてある。日本聖書協会『聖書 新共同訳』
ヨハネによる福音書 19章31節~37節
今日のところで、一人の兵士がイエスを槍で突き刺しますね。
「ロンギヌスの槍」というのを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
この兵士の名前がロンギヌスで、この槍が、聖なる槍であるという伝説があるんですね。
ただ、そもそもロンギヌスという名前は、槍という言葉が元になってできた言葉ですので、その時点でもう、どこまで信じていいのか分からないお話なんですが、この兵士、ロンギヌスは、白内障だったけれども、槍を刺した時にイエスの血が目に入って、視力が回復したというんですね。
それで、ロンギヌスは洗礼を受けてクリスチャンになって、今では、カトリック教会で聖人とされています。
それだけではなくて、この槍がものすごい力を持っているということになりまして、今で言うところのイギリスなんですが、アーサー王というこれまた伝説的な王がおりまして、その王様のお話にもこの槍が出てきます。
また、この槍を持つ者は世界を制する力が与えられるという言い伝えがありまして、アドルフ・ヒトラーがこの槍を探していたという、本当か噓か分からない話もあります。
現代では、いくつかのアニメにこの槍が登場してきたりもしますね。
とにかく、人の空想を刺激するような槍、ということになるでしょうか。
ただ、この槍についてのお話がこんなにも膨らんでしまったことは、分からないことではありません。
それは、今日のお話の後の方でお話ししたいと思います。
さて、今日の最初のところですが、「その日は準備の日」だったということですね。
準備の日というのは、安息日の準備の日ということで、安息日は土曜日ですので、その日は金曜日だったということですね。
翌日は「特別の安息日」ということですが、過越祭という、一番大事なお祭りが一週間かけて行われる期間の中の安息日、ということで、「特別の安息日」になります。
そして、この地域では、日が沈むと一日が終わって、新しい日になります。
今は金曜の午後ですから、安息日まで、もう、あと数時間しかないんですね。
ユダヤ人たちとしては、あと数時間で全部終えてしまいたい。
安息日は神に心を向ける大事な日ですから、死体を出しておきたくないんですね。
それで、死刑囚の足を折って殺してしまって、すぐに取り降ろすように、ローマ帝国から派遣された総督であるピラトに願い出ました。
十字架の刑というのは、時間をかけて苦しめて、人を殺す方法です。
十字架に付けられるときには、両肩の関節が外れるくらい腕を引っ張られて、磔にされます。
ですから、十字架に付けられると、胸を膨らませて息をすることができません。
死刑囚は、膝を曲げ伸ばしして、横隔膜を上下させて、息をします。
長い時間が経って、膝を曲げ伸ばしする体力がなくなって、窒息して死ぬ。
これが十字架です。
けれども、そこで足を折りますと、膝を曲げ伸ばしすることができなくなりますので、すぐに窒息して死んでしまうんですね。
十字架刑の場合、死ぬまでに3日かかった人もいたという事例もありますので、時間がない時にはそういうことをしていたようです。
兵士たちは、大きなハンマーで打ちたたいて、二人の死刑囚の足を折りました。
けれども、イエスはもう死んでいました。
十字架に付けられてから数時間で、もう死んでいた。
イエスは十字架に付けられる前に鞭で打たれていたんですね。
ローマ帝国の鞭というのは、一回打たれただけでも大量に出血するようなものでしたから、イエスは、最初から死にかけているような状態で十字架に付けられた。
だから、数時間しか命が持たなかったんですね。
ただ、この時に、このタイミングでイエスが命を落としたことには、大きな意味があります。
少し時間をさかのぼりますが、18章28節です。
18章28節から、イエスがピラトから尋問される場面が始まっていきますね。
それは、言ってみれば今日の場面の朝早くのことなんですが、その時、ユダヤ人たちは、総督の官邸に入らなかったんですね。
それは、「汚れないで過越の食事をするためである」と書かれていました。
ユダヤ人は、異邦人の家の中に入ると自分が汚れると考えていました。
これから過越の食事をするのに、汚れていてはまずいということで、中に入らなかった。
過越の食事は夜に食べます。
この時はまだ朝なんですが、この日、日が沈んで、夜になって、日付が変わると、過越の食事です。
つまり、この日は今日の場面と同じ日で、「準備の日」で金曜日ですが、日が沈んですぐの土曜日の夜になって、過越の食事が始まるということなんです。
そして、過越の食事では、小羊を食べるんですが、その小羊を屠るのは過越の食事のすぐ前の午後と決まっていました。
つまり、イエスは、過越の小羊が屠られる、ちょうどその時に、命を落としたことになります。
この福音書の1章29節で、イエスに洗礼を授けた洗礼者ヨハネがイエスを見つめて、「見よ、世の罪を取り除く神の小羊だ」と言っていました。
その昔、エジプトで奴隷にされていたイスラエルの人々が、神の言葉の通りに、小羊を屠って、その血を自分の家の玄関のドアの周りに塗った。
その家には神の裁きが下らなかった。
そのようにしなかったエジプト人の家には、神の裁きが下った。
こうして、イスラエルの人々は自由にされた。
それと同じように、神の小羊イエスが、私たちの罪を背負って、私たちの代わりに十字架にかかって犠牲になってくださったことによって、私たちの罪が取り除かれる。
イエスが私たちに代わって罪に対する裁きを受けてくださるから、私たちには罪の赦しが与えられる。
イスラエルの人々が、奴隷であったところから自由にされたように、私たちも、罪に支配されている罪の奴隷であり、神の裁きを受けるしかないところから、自由にされる。
イエスが、神の小羊として屠られたから。
今日の聖書の言葉は、私たちにそのことを伝えているんですね。
そして、これは面白いところなんですが、十字架と復活のイエスは、イスラエルのお祭りをなぞるんですね。
十字架は過越祭と重なることだ、というのは良く知られたことですが、それだけではないんですね。
レビ記23章には、イスラエルのお祭りが7つ、記されています。
まず、過越祭が祝われる1週間の中で、除酵祭というお祭りがあると書かれています。
これは、酵母を除くお祭りと書いて、除酵祭です。
酵母というのはパン生地に入れるイースト菌ですね。
イースト菌を入れずにパンを焼いたら柔らかいパンにならないんですが、エジプトで奴隷にされていたところから出ていくときには、パンに酵母を入れて発酵するのを待つ時間がありませんでしたから、酵母を入れずにパンを焼いた。
そのことを思い起こすお祭りなんですね。
そして、この酵母のことが、聖書では、いい意味でも、悪い意味でも使われることがあります。
酵母は、ほんの少し入れただけでも、小麦粉の塊全体が大きく膨らみますね。
そのように、ほんのちょっとあっただけでも、全体に大きく影響するもの、という意味で使われるんです。
イエスは、「ファリサイ派のパン種に気をつけなさい」と言ったことがありました。
ファリサイ派のように、自分の力で天国に入るんだ、という気持ちが少しでもあると、信仰全体が台無しになってしまうよ、ということですね。
けれども、除酵祭なんです。
酵母が除かれるんです。
十字架で、私たちの罪が除かれたわけです。
レビ記23章10節からは、初穂の祭りについて書かれています。
このお祭りも、過越祭の1週間の中で祝われるお祭りなんですが、1週間の中の安息日の翌日、日曜日のお祭りだとレビ記23章15節に書かれています。
日曜日はイエスが復活した日ですね。
そして、イエスが復活したのは、ご自分の力を自慢するためではありません。
イエスが復活の初穂だと新約聖書の後半に書かれますが、初穂なんですね。
最初の収穫なんです。
最初に復活したのはイエスです。
そして、後に続いて、他の人たちも復活させられるということなんですね。
イエスご自身、そういうことを言っておられたことが新約聖書に出てきます。
そして、その次のお祭りが、16節からの五十日のお祭りですね。
イエスが復活してから、50日後に何がありましたか。
イエスが約束していた通りに、聖霊が降ったんですね。
つまり、十字架と復活のイエスはイスラエルの祭りを完全に意識しておられると言うことができます。
そうなると気になるのは、イスラエルの祭りは、今申し上げた春のお祭りだけではなくて、秋のお祭りもありますから、春のお祭りはこれだけ意識しておいて、秋のお祭りのことを考えておられないということもないだろうと思うんですね。
春のお祭りは、十字架と復活だった。
では、秋のお祭りは何なのか。
再臨の時でしょうね。
イエスは、再びこの世に来られることを予告しておられますから、その時、秋の三つのお祭り、角笛の祭りと贖罪日、仮庵祭がなぞられていくんでしょうね。
それについてのお話はまたいつかしようと思います。
ただ、イエスが十字架にかかったのは金曜日だったというのは他の福音書と同じですが、他の福音書では過越の食事がいつだったのか、というのが違うんですね。
他の福音書では、過越の食事も金曜の夜だったと書かれているんです。
木曜の日が沈んですぐ後、金曜になると過越の食事をして、その後、イエスは逮捕されて十字架に付けられたと書かれているんですね。
でも、この福音書では、土曜になってからが過越の食事だと言われているんですね。
これが難しいところなんですが、この時代、ユダヤ人たちの間だけでも、いくつかの暦があったことが分かっています。
ユダヤ教にはファリサイ派とサドカイ派という二つの大きなグループがあったと聖書にも記されていますが、ファリサイ派とサドカイ派では、暦が違うんですね。
それだけでなく、また別のカレンダーもあったことが知られています。
ですから、これについては細かく考えても仕方がないのではないかと思います。
ただ、他の福音書では、十字架の前に、もう過越の食事は済んでいるので、だとすると当然、小羊はもうとっくに屠られて食べられてしまっているので、イエスの十字架と罪を取り除く小羊が関係なくなってしまう、イエスの十字架に、小羊の犠牲という意味がなくなってしまうと思われるかもしれません。
しかし、他の福音書では、過越の食事の場面で、イエスが、パンとぶどう酒を弟子たちに差し出しますね。
これは私の肉である。
これは私の血である。
ご自分の命を差し出してくださった。
イエスの命と引き換えに、神の裁きが過ぎ越すということでは同じなんです。
その中で、この福音書では、イエスは神の小羊だ、というところに焦点を当てているんですね。
十字架の場面に戻りますと、イエスは死んでいたんですが、兵士の一人がイエスの脇腹を刺しました。
本当に死んでいるのかどうかを確認したかったのでしょう。
そうすると、すぐに、血と水とが流れ出ました。
普通、死体からは血が流れ出ることはありません。
もし、血が流れ出るということがあるなら、それは、体の中に血がたまっていて、そこを突き刺したからだということになります。
おそらくこれは、イエスが十字架に付けられる前に鞭で打たれた際に、体の横側に血だまりができて、そこを突き刺したのではないかと思います。
血と水が流れ出たとありますが、死んだ後には血液が透明な血漿と赤い赤血球に分離するのだそうです。
ですので、血と水が流れ出たように見えるということですね。
ここで、この福音書を書いたヨハネは、何かやけに力を入れて書いています。
「それを目撃した者が証ししており、その証しは真実である。その者は、あなたがたにも信じさせるために、自分が真実を語っていることを知っている」。
「目撃した者」とはヨハネ自身のことでしょう。
このことは本当のことなんだ、と力説しています。
そして、その話から、これは聖書の言葉の実現だったんだ、という話につなげるんですね。
つまり、ここで引用されている聖書の言葉が実現したことが、それほど大事なことなんだということです。
まず、「これらのことが起こったのは、『その骨は一つも砕かれない』という聖書の言葉が実現するためであった」とあります。
「その骨は一つも砕かれない」という言葉によく似た言葉は旧約聖書の詩編にもあるんですが、イエスは神の小羊だというのがこの福音書ですから、そう考えますと、このところのことは、出エジプト記12章を意識して書かれたものであると考えられます。
出エジプト記12章43節からは、過越祭について書かれていまして、12章46節に、「その骨を折ってはならない」とあるんですね。
過越の小羊の肉を食べる際には、骨を折ってはならないという決まりがあるんですね。
その言葉の通りになった、イエスは骨を折られなかった、イエスは神の小羊だから、と言いたいんですね。
それだけではなく、「彼らは、自分たちの突き刺した者を見る」という言葉が挙げられていますが、これはゼカリヤ書12章10節です。
ゼカリヤ書12章10節にはこう書かれています。
「わたしはダビデの家とエルサレムの住民に、憐れみと祈りの霊を注ぐ。彼らは、彼ら自らが刺し貫いた者であるわたしを見つめ、独り子を失ったように嘆き、初子の死を悲しむように悲しむ」。
「彼ら自らが刺し貫いた者であるわたしを見つめ」、と書かれています。
「彼ら自らが刺し貫いた者であるわたし」というのは誰でしょうか。
神のことです。
彼らというのは、「ダビデの家とエルサレムの住民」ですから、神の民、神を信じる者たちということですね。
その人たちが、神を刺し貫くと言われているんですね。
実際に槍で刺したのはローマの兵士です。
しかし、けれども、ヨハネは、神の民である、イエスの弟子である自分が刺したんだというんですね。
イエスは神の小羊です。
世の罪を取り除く神の小羊です。
この私の罪が赦されるために、神の子が裁きを引き受ける。
自分の罪が、イエスを刺し貫いた。
その意味で、ヨハネは、私がロンギヌスだと言っているんですね。
しかし、だからこそ、私の罪のために刺し貫かれてくださったからこそ、イエスは神の小羊になったとも言えます。
そこで、ヨハネは力説するんですね。
イエスが神の小羊であること、自分の罪がイエスを刺し貫いたこと。
その両方を理解するところに十字架の救いがあるから、力を込めて語るんです。
ヨハネは言います。
「その者は、あなたがたにも信じさせるために、自分が真実を語っていることを知っている」。
ヨハネがこのことを言うのは、読む人に信じさせるためです。
現場で目撃したわけではなくても、読んで、信じるなら、救いにあずかることができるということなんです。
目撃した人だけではないんです。
槍で刺した人だけではないんです。
その意味で、私たちはみんなヨハネであり、ロンギヌスなんです。
だからヨハネは、骨が折られなかったとか、死んでいるか確認するために槍で刺されたとか、別にどうでも良いようなことを、一生懸命、語るんです。
人の救いが、ここのところにかかっているからです。
人が救われるかどうかが、この場面を信じるかどうかにかかっているからです。
その上、信じやすくするために、イエスは、過越祭だけでなく、イスラエルの春の祭りを全部なぞってくださいました。
これ以上に何か、信じることができるように、というのはちょっと思いつきません。
これで信じない人というのは最初から信じない人で、聖書の中にも出てくるような、たとえその目で奇跡を見ても信じない人ということなんでしょう。
だからこそ、やはり、この場面に人の救いがかかっていると言えます。
もとより、イエスは、文字通り命がけでこの場面に臨みました。
その命をいただきたいと思います。
その時、私たちは、伝説に言われるロンギヌスですね。
白内障だったけれども、槍を刺した時にイエスの血が目に入って、視力が回復した。
そうなるんだと思います。
私たちはみんな、自分が見えていると思っている。
自分は何が正しいか分かっていて、自分の頭で正しく判断できると思っています。
でもそれは、自分が知っているコップの中の世界でのことです。
大人は大人の世界のことを正しく判断できることもあるでしょうが、子どもだったときはどうだったでしょうか。
子どもも子どもなりに一生懸命生きていますが、子どもの世界のコップより、大人の世界のコップの方が大きいんです。
子どもからすると、大人の世界は広くて深くて見渡せない。
子どもは自分が見えていないとは思っていませんし、子どもなんだから子どものコップの中のことが分かればそれでいいんですが、大人の世界のことは分かりません。
それと同じことは、大人にも言えます。
大人だとしても、誰か一人の人のコップが、世界のすべてではない。
世界の一部とすら言えないくらいでしょう。
まして、世界を造った神の世界は広いんです。
そして、私たちは、神の世界については白内障というか、ほぼ何も見えていないでしょう。
しかし、その、神の世界に目が開かれることはあるんですね。
だから、今日、聖書は私たちに語りかけているんです。
あなたがたにも信じさせるためだ、と。
これから聖餐式にあずかります。
小羊の肉と血をいただきましょう。