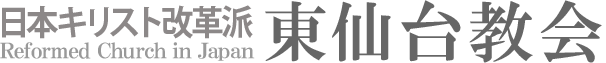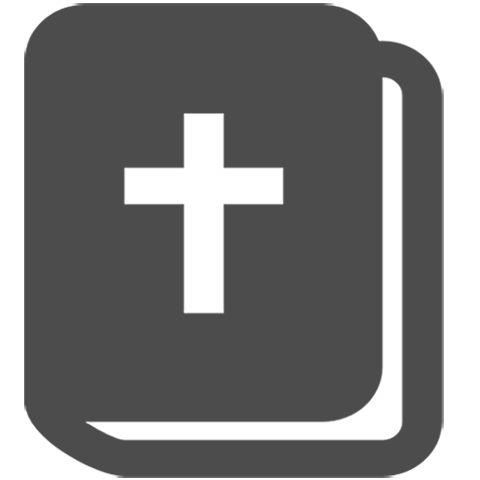成し遂げられたこと
- 日付
- 説教
- 尾崎純 牧師
- 聖書 ヨハネによる福音書 19章25節~30節
25イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。26イエスは、母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、「婦人よ、御覧なさい。あなたの子です」と言われた。27それから弟子に言われた。「見なさい。あなたの母です。」そのときから、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。
28この後、イエスは、すべてのことが今や成し遂げられたのを知り、「渇く」と言われた。こうして、聖書の言葉が実現した。29そこには、酸いぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々は、このぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプに付け、イエスの口もとに差し出した。30イエスは、このぶどう酒を受けると、「成し遂げられた」と言い、頭を垂れて息を引き取られた。日本聖書協会『聖書 新共同訳』
ヨハネによる福音書 19章25節~30節
今日の場面が、イエスが十字架の上で、最後に言葉を発する場面ですね。
クリスチャンのお医者さんで、聖路加国際病院の院長であった日野原重明さんは、多くの方の最後を看取った方でもありますけれども、死の間際に言葉を残して死んでいくのは人間だけであると言っています。
そもそも、言葉を話すのは人間だけなんですが、死の間際の言葉に、その人の一生のすべてが凝縮されている、ということはあると思うんですね。
それが、イエスの今日の言葉です。
その時、イエスの十字架のそばには、四人の女性がいました。
四人の女性と一人の男性の弟子がいたんですが、ここで四人の女性が並べられているのは、このすぐ前の場面で、イエスの服を取り合った兵士たちが四人だったからでしょう。
四人の兵士たちがくじを引いて、イエスの服を取り合っている。
その同じ場所に、四人の女性たちが立ってイエスを見上げている。
この四人の中で、まず、二人目に紹介されている「母の姉妹」に注目したいと思います。
母というのはイエスの母、マリアですね。
母の姉妹というのは誰かというと、この人のことが、マタイによる福音書の27章56節では、「ゼベダイの子たちの母」と書かれています。
そして、「ゼベダイの子たち」というのは、十二弟子にいたわけですね。
イエスが直接選んだ十二人の弟子たちの内の二人が、ゼベダイの子のヤコブとヨハネでした。
そして、その二人の母親がイエスの母マリアの姉妹なんです。
つまり、弟子のヤコブとヨハネはイエスのいとこなんですね。
そして、この場には、そのヨハネもいるんですね。
ここに、イエスの「愛する弟子」というのがいますけれども、これは、ヨハネのことであると考えられています。
イエスからすると、自分の母がいて、母の姉妹がいて、その息子、自分のいとこもいる、という状況です。
そこで、イエスは不思議なことを言いました。
「婦人よ、御覧なさい。あなたの子です」。
これは、母のマリアに言ったことですね。
次に、弟子のヨハネにも言われました。
「見なさい。あなたの母です」。
そして、そのときから、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取ったというんですね。
これはどういうことでしょうか。
イエスが、これから死ぬことは承知しておられたけれども、母親のことが心残りで、自分の弟子に託したということでしょうか。
イエスは最後に、母親に対して心配しなくていいよ、と言ったということなんでしょうか。
そうではありません。
イエスは自分の母親のマリアに、「婦人よ」と呼びかけているんです。
自分を産んだ母親に対する愛情だというなら、そんな言葉遣いはおかしいでしょう。
ではどうして、「婦人よ」なのか。
実は、「婦人よ」という言葉が、この福音書の中で、ずっと前にイエスの口から語られたことがありました。
2章4節ですね。
カナというところで結婚式があって、イエスもマリアもそこにいました。
その時、ぶどう酒がなくなってしまいました。
それを知ったマリアがイエスに相談するんですが、それに対してイエスは答えたんですね。
「婦人よ、わたしとどんなかかわりがあるのです。わたしの時はまだ来ていません」。
その時も、自分の母親に対して、「婦人よ」と言ったんですね。
しかも、それに続けて、「わたしとどんなかかわりがあるのです」と言ったんですね。
これは大変な言葉です。
母でもなければ子でもないと言ったんですね。
そして、続けて、「わたしの時はまだ来ていません」と言ったんです。
ではこの「わたしの時」とは何でしょうか。
それは、十字架の時ですね。
イエスは、十字架の時が近づくと、「わたしの時が来た」ということを言い始めました。
そして、今日のところでも、「そのときから、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取った」と書かれています。
今日、その時になったんです。
イエスの時になったんです。
だから、この弟子は、イエスの母を引き取ったんです。
イエスの母を、自分の母にしたんです。
もう、どこの誰か分からない「婦人」ではないんですね。
母になったし、子になった。
ただ、「母と子」になるというのは、マリアとイエスの間に実現したことではないんですね。
マリアとヨハネの間に実現しているんです。
そして、また別に、ここには不思議なことがあります。
イエスの母はマリアだと誰でも知っています。
でも、名前は出てきていません。
そして、この福音書に何度も出てくるイエスの愛しておられた弟子というのは、ヨハネのことだというのも、知っている人は知っている話です。
けれども、それがヨハネだとは一度も語られていないんですね。
そもそも、イエスが愛しておられた弟子は、ヨハネだけではありません。
この福音書の13章1節にはこう書かれています。
「イエスは、この世から父のもとへ移る御自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた」。
弟子たちは皆、愛されているんです。
ですから、この福音書に出てくる「イエスの愛しておられた弟子」というのは、弟子たちみんなのことです。
イエスの弟子ってこういうものだよね、という一つの見本なんです。
そういう、象徴的な意味で、「イエスの愛しておられた弟子」と言われているんですね。
つまり、ここの話は、イエスの弟子には母が与えられるものなんだ、という話なんです。
肉親の母親とはまた別に、母親が与えられるんですね。
それは、マリアのことではありません。
ここに、マリアという名前は出てきていません。
他のマリアはここに名前が出ているのに、この母には名前がないんですね。
ですから、母が与えられるというのも、象徴的な話なんですね。
ではこの母とは何なのか。
母とは、この私を産んだ存在です。
もちろん、肉親の、血がつながった私の母は私を産んだのですが、私が産まれる、というのは、それだけではありません。
この福音書の3章3節で、イエスはこう言っていました。
「人は新たに生まれなければ、神の国を見ることはできない」。
3章5節にはこうあります。
「だれでも水と霊とによって生まれなければ、神の国に入ることはできない」。
この、「水と霊とによって生まれる」というのは、洗礼のことですね。
当時の洗礼式は、川で行われることが多かったのですが、全身水に浸かって、そこから上がってくる。
それによって、一度死んで、新しく生き始める、ということなんですね。
新しい命に生まれる。
そして、洗礼という言葉は、原文では、「どっぷり浸かる」という言葉なんですが、水に浸かるだけでなく、霊にも浸かるんですね。
その、私たちが新しく生まれる、水と霊とによる洗礼を執り行うのが、教会です。
私たちは教会において、洗礼を授けられて、父なる神の子とされるんですね。
そして、母なる教会が私たちを産むだけでなく、育ててくれる。
そして、その母は私たちの母であると共に、イエスの母ですから、教会において私たちは、イエスの兄弟姉妹とされるんですね。
そして、イエスと共に、神を父と呼んで祈るんですね。
ですから、私たちが教会につながっているというのは決定的なことです。
私たちが教会につながっているからこそ、私たちは、神の子として新しく生まれた者であり、神が父であり、イエスの家族であり、私たちはお互いに兄弟姉妹なんですね。
イエスは最後の最後に、そのようになるようにしてくださったんです。
イエスは、すべてのことを成し遂げました。
そのことをご自身で知りました。
その時、「渇く」と言われました。
喉が渇いたということでしょうか。
何時間も十字架に張り付けにされているのですから、当然と言えば当然です。
しかしこれが、聖書の言葉が実現することだったというんですね。
旧約聖書の詩編22編16節です。
そこに、「口は渇いて素焼きのかけらとなり 舌は上顎にはり付く」とあります。
喉が渇くことが書かれているんですね。
それだけのことだったら、わざわざ、聖書の言葉が実現した、と言わなくても良いような気がしますが、詩編22編には十字架と重なる表現がたくさん出てきます。
今日の場面のすぐ前の場面にも、聖書の言葉が実現した、とありましたが、そちらも、詩編22編です。
他にも、詩編22編と十字架のイエスが重なる点がいくつかあります。
ですから、イエスは、詩編22編をなぞるようにして十字架にかけられたと言っていいんですね。
詩編22編では、どうしようもないくらいの苦難が綴られますが、最後には、神が救い出してくださること、神への賛美が地上に広がっていくことが描かれます。
イエスは、それへの道を付けてくださったんですね。
人々は、スポンジを木の枝に付けて、スポンジに酸いぶどう酒を含ませて、イエスに飲ませました。
酸いぶどう酒というのは、お酒ではなくて、ぶどうで作ったお酢で、ローマの兵士は普段、それを水で薄めて飲んでいたようです。
しかし、これをそのまま飲んだのでは、余計に喉が渇いたことでしょう。
そんなものを飲ませるとは何事か、と思うのですが、イエスはそれを受けられました。
イエス自身が言っておられた言葉を借りるなら、「父がお与えになった杯は飲むべきではないか」ということでしょうか。
杯というのは、神が与える苦難を意味する言葉ですね。
だからイエスはこれも飲んだ。
もしかすると、「渇く」と言ったのも、喉が渇いたということではなく、飲み干した、杯が渇いた、苦難をすべて受け切った、という意味で言ったのかもしれません。
最後にイエスは、「成し遂げられた」と言い、頭を垂れて息を引き取られました。
この「成し遂げられた」という言葉と、もともとの言葉としては、同じ言葉が、先ほど紹介した、この福音書の13章1節に出てきます。
「イエスは、この世から父のもとへ移る御自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた」。
その「この上なく」という言葉を「この上なく行う」という形にして、完了形にしたのが、今日の「成し遂げられた」なんですね。
完全に完了した、という感じなんです。
弟子たちをこの上なく愛し抜かれたイエスが、その愛を完全に全うしてくださったということです。
イエスが私たちに対する愛を全うしてくださって、私たちは、神の家族とされ、主にある兄弟姉妹とされているんです。
信じられないことです。
信じられないというより、考えもつかないようなことです。
望むこともできないようなことです。
しかし、イエスはここで、それを、成し遂げられたと言ってくださっているんです。
またこの「成し遂げられた」という言葉は、負債を完済する、借金をすべて返し終わる、という意味でも使われた言葉です。
聖書では、罪というものが、負債、借金に例えられることが良くあります。
罪も借金も、償わなければ、返さなければ、なくならないからです。
イエスは、私たちの罪の負債をすべて肩代わりして、支払ってくださいました。
それが十字架で、罪のない方が罰を受けるということでした。
イエスが十字架で、私たちの負債を、すべて返済してくださいました。
そして、神である方が、完全に返済した、と宣言してくださっているんです。
ご自分の命を懸けてそうした、と。
神の子の死の向こうに、私たちは新しく生かされることになったんです。
イエスは最後、頭を垂れて息を引き取られました。
「頭を垂れる」は他のところでは「枕する」と訳されている言葉です。
イエスが言っておられましたね。
マタイによる福音書8章20節ですが、「狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕する所もない」。
今までは、枕するところもないほど、働いてこられました。
ようやく、すべての務めを終えて、枕するところにたどり着いたんですね。
それは、十字架の上だったんですが。
「息を引き取った」とも書かれていますが、これは原文では、「霊を渡した」という言葉です。
渡す、というのは、イエスを十字架に引き渡すというのと同じ言葉です。
枕して、霊を渡した。
すべて、ご自分でなさって、ご自分で幕を引いた。
それでいいんです。
私たちにできることは何もありません。
私たちにわずかでも介入できることは今日の場面に一切ありません。
すべて、イエスがなさってくださいました。
なさってくださって、宣言してくださいました。
「あなたの子です」、「あなたの母です」、「成し遂げられた」。
だから、私たちは、救われているんです。