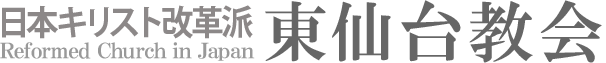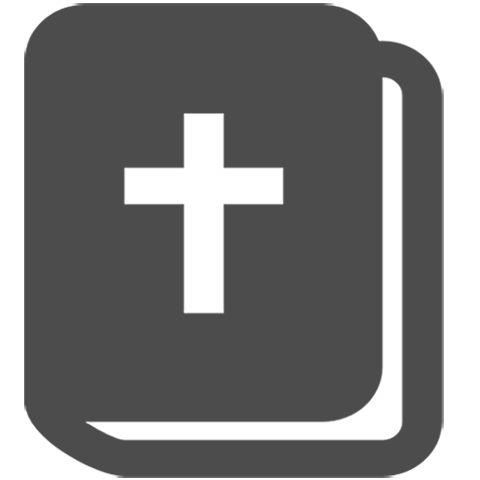どういう罪でこの男を訴えるのか
- 日付
- 説教
- 尾崎純 牧師
- 聖書 ヨハネによる福音書 18章28節~40節
28人々は、イエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし、彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで過越の食事をするためである。29そこで、ピラトが彼らのところへ出て来て、「どういう罪でこの男を訴えるのか」と言った。30彼らは答えて、「この男が悪いことをしていなかったら、あなたに引き渡しはしなかったでしょう」と言った。31ピラトが、「あなたたちが引き取って、自分たちの律法に従って裁け」と言うと、ユダヤ人たちは、「わたしたちには、人を死刑にする権限がありません」と言った。32それは、御自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、イエスの言われた言葉が実現するためであった。33そこで、ピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、「お前がユダヤ人の王なのか」と言った。34イエスはお答えになった。「あなたは自分の考えで、そう言うのですか。それとも、ほかの者がわたしについて、あなたにそう言ったのですか。」35ピラトは言い返した。「わたしはユダヤ人なのか。お前の同胞や祭司長たちが、お前をわたしに引き渡したのだ。いったい何をしたのか。」36イエスはお答えになった。「わたしの国は、この世には属していない。もし、わたしの国がこの世に属していれば、わたしがユダヤ人に引き渡されないように、部下が戦ったことだろう。しかし、実際、わたしの国はこの世には属していない。」37そこでピラトが、「それでは、やはり王なのか」と言うと、イエスはお答えになった。「わたしが王だとは、あなたが言っていることです。わたしは真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆、わたしの声を聞く。」38ピラトは言った。「真理とは何か。」38ピラトは、こう言ってからもう一度、ユダヤ人たちの前に出て来て言った。「わたしはあの男に何の罪も見いだせない。39ところで、過越祭にはだれか一人をあなたたちに釈放するのが慣例になっている。あのユダヤ人の王を釈放してほしいか。」40すると、彼らは、「その男ではない。バラバを」と大声で言い返した。バラバは強盗であった。日本聖書協会『聖書 新共同訳』
ヨハネによる福音書 18章28節~40節
人々はイエスを総督官邸に連れて行きました。
最高権力者のところにイエスを連れて行ったんですね。
その人々のことが、ユダヤ人の権力者たちとは書かれませんでして、単に「人々」と書かれています。
人は神の子を殺そうとするものだということでしょうか。
そうかもしれません。
人間というものは罪人であると聖書は言いますが、神に従うよりも自分が神になりたいというのが人間です。
特別な人でもない、ただの「人々」が神の子を殺すんです。
しかし、この時のことが、「明け方であった」と書かれています。
そんなことは書かなくてもいいことです。
しかし、そのように言われるんですね。
それに対して、ユダが裏切って出て行った時には、「夜であった」と書かれていました。
そこから、闇の時間が始まります。
しかし、今ここで、「明け方であった」と書かれます。
もうすぐ、光の時間が始まるのです。
人間の目にはこの場面は闇の時間が続いているようにしか見えません。
しかし、人間の目にそうであるところで、実は、光の時間が始まっているということがあるわけです。
それにしても、イエスを連れて行ったこの人々の様子はどうでしょうか。
「彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで過越の食事をするためである」と書かれています。
異邦人であるピラトの官邸に入ると、自分が汚れてしまって、お祭りの大事な食事ができなくなる。
過越祭というのは一番大事なお祭りですが、過越祭の中心になるのが過越の食事でしたから、それを大事にしたということですね。
しかし、これはどうなんでしょうか。
彼らは、彼らの良識に従って、また、自分の都合で、自分がお祭りの食事をすることを大事にしている。
でも、無実の人に罪を着せて殺してしまうことは平気なんですね。
やはり、罪人なんです。
それは、私たちもです。
私たちにも、良識があるように装いながら、本当のところ自分の都合を優先して、そのために、もっと大事なことが頭から抜けてしまうことがあります。
考えてみると、私は毎日、そういうことがあります。
おそらく、多くの人もそうでしょう。
それはもしかすると、言いようによっては、イエスを十字架に付けるようなことだったかもしれない。
今日のこの人々と私たちに、大きな違いはないんです。
でも、今この時が「明け方」なんです。
ここから夜明けの時が来るんです。
この人々にも、私たちにもです。
ここで一つ、説明しておくべきことがあります。
他の福音書では、イエスと弟子たちがした最後の食事、いわゆる最後の晩餐が過越の食事だったと書かれています。
けれども、この福音書では、過越の食事はまだなんだということになっていますね。
ですから、ヨハネだけが、違うタイムテーブルで書いていると言われることがあります。
ただ、これは何も、ヨハネだけが違うことを書いていると考えなくても良いように思います。
まず、過越の食事というのは、一番大事なメインの食事があったんですが、その他にも、別の日に、神に備えたもののおさがりを食べるということが何度かあったんですね。
ですので、ここでいうところの過越の食事というのは、そのことを指しているのかもしれません。
あるいは、この人々も過越の食事をしようとしていたんだけれども、ユダが裏切りまして、イエスの居場所が分かりましたから、それだったらすぐに捕まえようということで、急に出ていかなければならなくなって、過越の食事をする時間が無くなってしまって、裁判が終わって家に帰ったら食事をしようということだったかもしれないんですね。
要は、この人たちだけは、まだ、過越の食事ができていなかったということです。
また、この時代には、カレンダーというのは一種類だけではなかったんですね。
ユダヤ教の中でも、ファリサイ派はファリサイ派のカレンダーを持っていましたし、サドカイ派はサドカイ派のカレンダーを持っていたんです。
ですので、この人々の中でも、いつ過越の食事をするのかというのは違っていたかもしれないんですね。
そういうことを考えますと、ヨハネだけが他の福音書とは違うタイムテーブルで書いているとは断定できないと思います。
とにかく、人々は官邸の中には入ってきません。
仕方がないのでピラトが出てきて言いました。
「どういう罪でこの男を訴えるのか」。
彼らは答えて、「この男が悪いことをしていなかったら、あなたに引き渡しはしなかったでしょう」と言いました。
これは最高権力者に対する言葉としてはどうなんでしょうか。
質問に答えていないんですね。
それどころか、どこか、上から目線です。
ですけれども、ピラトには、地元の人からそんなふうに言われても言い返せない事情があったんですね。
ピラトはローマ帝国から派遣された高級官僚だったわけですが、これまでに政治の上で大きなミスをしていまして、ユダヤの地元の人からローマ帝国に訴えられてしまったことが2度もあったんです。
ですので、ピラトとしては、地元の権力者たちを怒らせたくはないんですね。
人々が、「この男が悪いことをしていなかったら、あなたに引き渡しはしなかったでしょう」と言ったのも、あなたがちゃんとやらないと、訴えますよ、という脅しのつもりだったかもしれません。
それに対して、ピラトは、「あなたたちが引き取って、自分たちの律法に従って裁け」と言いました。
ピラトは関わりたくないんですね。
これは、ピラトが、この問題が信仰の上での問題であることを理解していたからでしょう。
ローマ帝国は、信仰の上での問題については関与せず、地元の人たちの自由に任せました。
だからこそ、大帝国を築くことができたのです。
しかし、ユダヤ人たちは、「わたしたちには、人を死刑にする権限がありません」と言いました。
ユダヤの文献にも、ちょうどこの時代に、人を死刑にする権限がローマ帝国に奪い取られたと書かれています。
けれども、新約聖書の使徒言行録を見ますと、ステファノは石打の刑で殺されています。
石打の刑というのはユダヤの死刑の方法です。
ただ、ステファノが殺されたのは信仰の上での問題でした。
ということは、信仰の上での問題なら、死刑にできたということなのでしょう。
そうだとしたら、ユダヤ人たちが、「わたしたちには、人を死刑にする権限がありません」と言ったのは、これは信仰の上での問題ではありません、と言ったことになります。
本当のところは、信仰の上での問題ではなくて、ファリサイ派にもサドカイ派にも属していない、フリーの立場のイエスが民衆に人気があることを、権力者たちが疎ましく思ったから殺そうとしているわけなんですが、権力者たちからすると、自分たちの手でイエスを殺すと、自分たちが民衆から批判されますから、それを恐れて、ローマ帝国に死刑にさせようとして、こう言ったんですね。
ただ、こう言われてしまいますと、ピラトとしても、何もしないわけにはいきません。
何もしなかったら自分が訴えられるでしょう。
ただここで、32節に不思議な言葉が書かれています。
「それは、御自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、イエスの言われた言葉が実現するためであった」。
問題が信仰の上でのことから、政治のことにすり替わってしまったのは、イエスの言葉が実現したことだったと言っているんですね。
どのような言葉があったかと言いますと、例えば12章32節、33節にはこうあります。
「わたしは地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとに引き寄せよう」。
これは、自分は十字架にかかって死んで神の元に帰るけれども、その時に、すべての人が神の元に帰ることができるように、私が道を付けるということですね。
そして、ここで、ご自分が死ぬことを、「地上から上げられる」と言っているわけです。
これは、石打の刑ではないですね。
石打の刑だったら地面に倒れます。
十字架は上げられることです。
イエスは、ローマ帝国の死刑の方法で殺されることを知っていたんですね。
この福音書の3章14節、15節には、もっとはっきりとしたことが言われています。
「モーセが荒れ野で蛇を上げたように、人の子も上げられねばならない。それは、信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである」。
旧約聖書のモーセの時代に、蛇にかまれて死ぬ人が多く出たことがあったんですが、モーセが竿の先に掲げた青銅の蛇を見上げると、蛇にかまれた人も助かったんですね。
その、青銅の蛇と同じように、自分も上げられるということですから、やはりこれは石打の刑ではないんですね。
十字架に上げられた自分を見上げる者は救われるということです。
そのイエスの言葉が実現するために、この時のユダヤ人たちとピラトのやり取りがあったということなんですね。
ピラトは官邸の中に戻りまして、イエスに尋ねます。
「お前がユダヤ人の王なのか」。
ピラトはイエスのことをある程度聞いていたんでしょう。
信仰の上での問題だと思うけれども、現実問題、王でも何でもない人間が、「ユダヤ人の王」だと名乗っているらしい。
信仰の上での問題ではないということなら、ユダヤ人たちはそこを問題にしているのだろう。
現実問題、王でも何でもないわけですし、本当のところ、「ユダヤ人の王」という呼び名は、旧約聖書に救い主のことがそのように書かれているということであって、それはもうこの世の王のことではないですし、イエス自身はそのように言ったことはないんですが、本当に王だというつもりなんだったら、ローマ帝国に対する反逆になりかねませんから、ピラトとしてはそれを質問したんですね。
ただ、この質問の言葉は、原文では、ピラト自身はそう思っていないことをほのめかすような言葉になっています。
お前みたいなのが、ユダヤ人の王だというのか、という感じの言い方なんですね。
イエスは答えました。
「あなたは自分の考えで、そう言うのですか。それとも、ほかの者がわたしについて、あなたにそう言ったのですか。」
ピラトは話に聞いただけです。
そして、そうは思っていません。
ただ、この言葉は何でしょうか。
イエスは何を確かめたいんでしょうか。
それはもちろん、自分の考えなのか、人から聞いただけで、自分ではそう思っていないのか、ということです。
でも、それが大事なんですね。
イエスが何者であるかは、人がどう言っているのかという問題ではなくて、自分がどう考えるのか、という問題なんです。
これは、ピラトに対してだけ向けられた質問ではありません。
イエスがすべての人に問うていることです。
これはもちろん、問われるべきことです。
何しろ、モーセが荒れ野で青銅の蛇を上げたとき、それを見上げた人だけが救われました。
十字架も同じです。
十字架のイエスを見上げる者が救われるんです。
青銅の蛇であれ、十字架のイエスであれ、自分には無関係だと思っている限り、救われることはありません。
ですから、このイエスの問いは、決定的な問いです。
けれども、ピラトはユダヤ人たちに追い込まれていて、それどころではありません。
もっと大事なことが問われているんですが、それよりも、目先の自分の都合を優先してしまいます。
ピラトは言い返しました。
「わたしはユダヤ人なのか。お前の同胞や祭司長たちが、お前をわたしに引き渡したのだ。いったい何をしたのか。」
まず、「わたしはユダヤ人なのか」、私はユダヤ人ではないということですね。
だから、お前が何者なのか知らないし、関心もない、お前は一体何なんだ。
考えてみると、私たちも、イエスから、あなたは私を何者だというのか、と問われた場合、最初は同じことを答えるのではないでしょうか。
最初は皆同じです。
自分には関係がないし、関心もない。
ある意味、それは正しいんです。
どうして、青銅の蛇を見上げたら救われるのか。
どうして、十字架を見上げたら救われるのか。
それを定めたのは人間ではありません。
神が定めたことです。
ですから、人間にはそれとこれとは別問題だとしか思えません。
ただ、それでは誰も救われないことになります。
ですから、イエスはおっしゃってくださいます。
「わたしの国は、この世には属していない。もし、わたしの国がこの世に属していれば、わたしがユダヤ人に引き渡されないように、部下が戦ったことだろう。しかし、実際、わたしの国はこの世には属していない。」
ここでの「国」という言葉は、「王国」という言葉です。
イエスは自分が王であると言いました。
ただ、「わたしの国は、この世には属していない」んですね。
これは、「わたしの国は、この世からではない」という言葉です。
この世の力によって成り立っているわけではないということで、この世ではない、神からの力によるのだ、ということです。
ピラトはここで、自分の頭の中を整理した方が良かったでしょう。
最高権力者を前にして、平然とこんな受け答えができる人はまずいないでしょう。
まして、その人は、権力者が恐れるほど、多くの人に信頼されていたんです。
ただ、ピラトの頭の中は今までと同じです。
イエスが「王国」と言ったので、ピラトは、「それでは、やはり王なのか」と聞きました。
イエスは答えました。
「わたしが王だとは、あなたが言っていることです」。
確かにそうです。
王ということを持ち出したのは、ピラトです。
大事なのは、王だと言っているとして、本当のところ、どう考えているのか。
あなたはイエスを何者だと言うのか。
そのことが問われています。
イエスはさらに続けます。
ピラトが表面的なところで立ち止まってしまっているからでしょうか、さらにこう言いました。
「わたしは真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆、わたしの声を聞く。」
イエスの働きは証言することです。
真理について証しする、と言われていますが、イエスが今までしてきた話は、結局のところ、神の言葉を伝えることでした。
神の言葉に真理があるんですね。
そして、「そのために、この世に来た」。
神の元から来た。
そして、「真理に属する人は皆、わたしの声を聞く」。
属する、という言葉がまた出て来ましたが、こちらも「真理からの人」という言葉です。
決定的なことが言われてしまいました。
真理からの人でなければ、イエスの話は聞けないんですね。
私たちは罪人であって、もちろん、神の元から来たということではないんですが、この世にあっても、「真理からの人」というのと、「真理からではない人」というのはいるんですね。
真理を聞いた時に、それが真理だと分かる人と、そのような感覚を最初から持っていない人がいる、ということでしょうか。
現実問題、それはそうだと言えそうです。
ピラトはそのような感覚を持っていませんでした。
ピラトは言いました。
「真理とは何か。」
これは、真理を求めて質問した言葉ではありません。
ピラトはすぐにここから出ていきましたから、ピラトとしては、もうこれ以上話をしても仕方がないと思ったということです。
ピラトとしては、いったい何の話だ、という気持ちで言ったことです。
ただ、ピラトには、イエスが政治犯ではないことは分かりました。
そこで、「わたしはあの男に何の罪も見いだせない」と言いました。
ただ、そう言っただけではユダヤ人たちは納得しないと思ったのでしょう、イエスを釈放することを提案しました。
しかし、人々は、強盗を釈放することを求めました。
そして、ピラトは結局、強盗を釈放し、罪のない方を十字架に付けるしかなくなってしまいます。
皆さんはここでのピラトの様子をどうご覧になりますでしょうか。
最高権力者であるはずなのに、まるで召使です。
ユダヤ人は外にいて、中に入って来ない。
そのユダヤ人たちに脅されると、言うことを聞かなければならない。
自分が官邸の中と外を往復して、取次ぎをする。
何とかして分かってもらおうとしても、聞き入れてもらえない。
どうしてそうなってしまったんでしょうか。
それは、イエスが何者であるのかということについて、自分の答えを持たなかったからだと言えるでしょう。
真理を求めず、むしろそこから目を逸らして、この世の力関係の中で、うまく立ち回ろうとした。
その結果、自分にとっても不本意なことになってしまった。
これは、私たちも気を付けるべきことです。
真理を向き合うことなく、この世を生きていこうとするなら、結局のところ、この世の力に翻弄されて、正しくないと知りながら、それを止められないという不本意な生き方しかできません。
うまく立ち回っているようで、実は滑稽な生き方になってしまうのです。
大事なのは、真理を求めることです。
それは、現実とかけ離れた空想をすることではありません。
イエスは、この世の現実のただなかに来てくださったというのが、まさに今日の場面です。
そして、人間の罪や弱さをすべて背負ってくださって、十字架に上げられてくださったということなんです。
ご自身は、この場面でも、一切揺るがずにです。
それが、この世で現実に起こったことです。
十字架のイエスを見上げましょう。
この世を超えて揺るぎないものが、そこから与えられます。
先週、私の義理の父が天に召されました。
義理の父は歯磨き粉などで知られているライオンという会社に勤めていたんですね。
ライオンはキリスト教主義の経営をするということを看板に掲げていましたから、父はその会社に入ったのだそうです。
その父に、ある困難があったそうです。
当時、多くの会社が苦しめられていたことですが、総会屋ですね。
暴力団の組員が株主総会にやってきて、無茶苦茶なことを言って、議場を荒らすんですね。
それをされたくなかったら金を出せということです。
何か、今日の場面のユダヤの権力者たちも総会屋のようでもありますけれども、総会屋というのは、会社側からすると、大変に迷惑な話です。
多くの会社はお金を出して、静かにしてもらっていたんですね。
父はお金を出しませんでした。
しかし、お金を出さなかったらどうなるか。
父は祈りました。
自分が揺るぎなく、毅然と受け答えができるように。
株主総会が始まりました。
予想通り、総会屋が大声で無茶なことを言い始めました。
でもその時、不思議なことが起こりました。
総会屋の怒鳴り声が、赤ちゃんの声で聞こえたんだそうです。
そんなふうに聞こえたのは父だけでした。
でも、それで、揺るぎなく、毅然と受け答えができて、総会屋もあきらめて帰って行ったんだそうです。
十字架の主を見上げましょう。
私たちがこの世の闇に揺るがせられることのないように、主が助けてくださいます。
イエスは、言うだけ言って、後は私たちに丸投げということはなさいません。
イエスは、言ったことにご自分で責任を取ってくださいます。
聖書に書かれている、イエスの弟子たちに対する扱いというのはすべてそうですね。
だから、逃げ出した弟子たちが、後になって、どんなことがあっても揺るがない者になっていったんです。
安心して、十字架の主の元で、十字架の主を見上げましょう。
主が助けてくださいます。